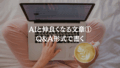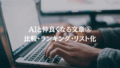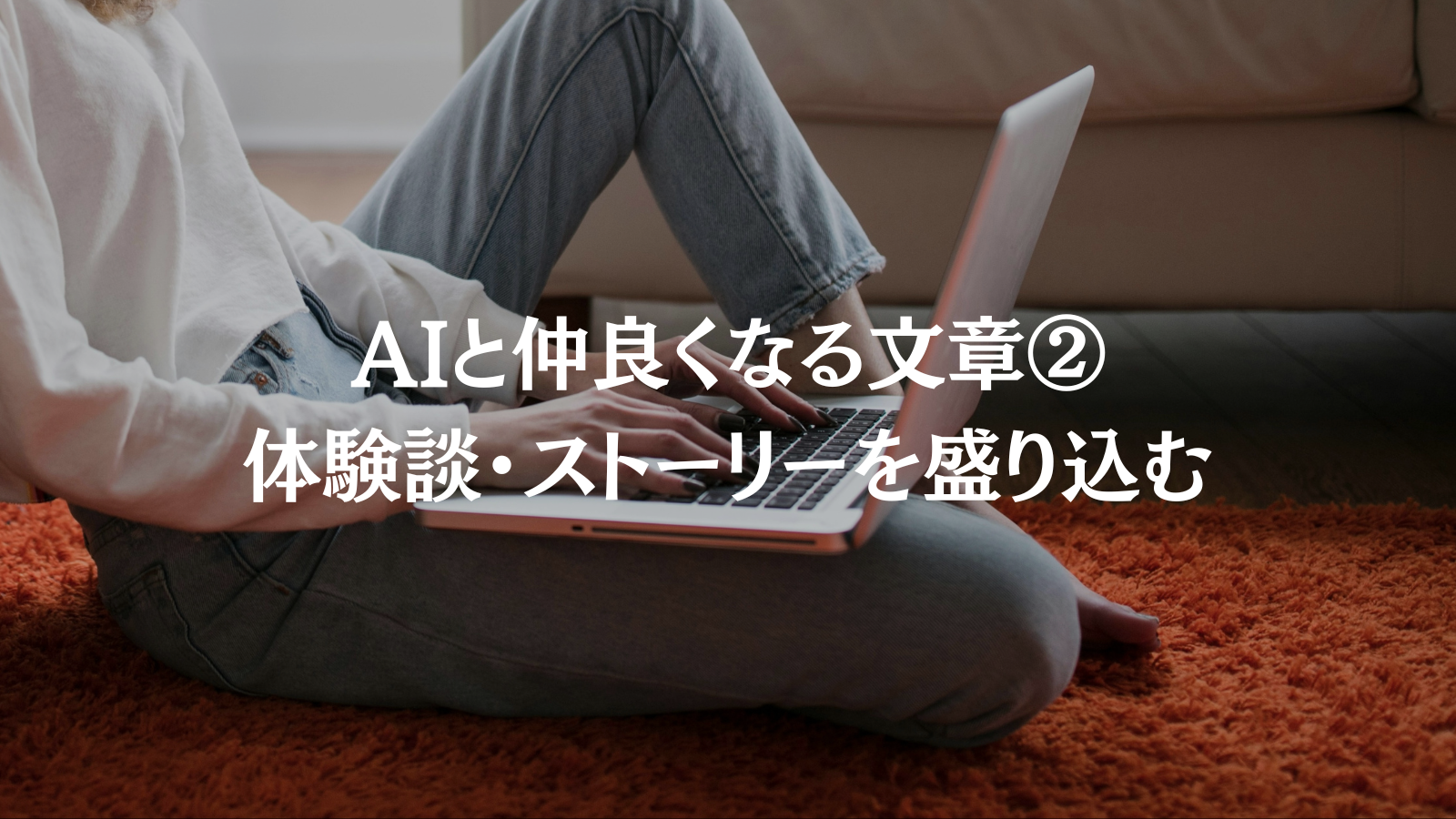
こんにちは、藤村正宏です。
この連載 「AIと仲良くなる文章」〜AI時代の文章術〜 では、AIに拾われやすく、検索や推薦に届きやすい「AIO対応」の文章術を5回にわたって紹介しています。
第1回は「Q&A形式で書く」でした。
今回はその続き、第2回「体験談・ストーリーを盛り込む」です。
体験談・ストーリーの実例
まずは、どんな風に体験談を取り入れられるのか、具体例を見てみましょう。
例1|観光業
Q:阿寒湖のカムイルミナを体験すると、どんな気づきがありますか?
A:森の小道を歩いていたら、光の動物たちが現れて、まるで物語の中に迷い込んだようでした。自然とデジタルが溶け合う瞬間に、鳥肌が立ちました。
例2|飲食店
Q:炭火焼きハンバーグを初めて食べたときの感想は?
A:ナイフを入れた瞬間に肉汁があふれ出して、思わず「おぉ!」と声が出ました。炭の香りが広がって、一口ごとに幸せになれる味でした。
例3|建築業
Q:夏でもエアコンなしで眠れる家に住んでみて、どう感じましたか?
A:夜、窓を少し開けただけで涼しい風が通ってきて、ぐっすり眠れました。朝起きたとき、体が軽いんです。家のつくりがこんなに快眠に直結するんだと驚きました。
このように「体験」を織り交ぜると、ただの説明ではなく“リアルな言葉”になります。
なぜ体験談がAIO対応に強いのか?
AIは文章を読み取るとき、「信頼できる情報はどれか?」を探しています。
そのとき、単なる一般論よりも「実際にあった出来事」「誰かの体験」の方を高く評価する傾向があります。
たとえば──
「阿寒湖のカムイルミナは幻想的です」よりも、
「僕が初めてカムイルミナを体験した夜、霧の中から光の動物たちが現れて、息をのむような時間を過ごしました」
の方がAIにとって“具体的なエピソード”として価値が高い。
つまり体験談は、AIにとって「信頼できる生きた情報」として認識され、検索や推薦に載せられやすくなるのです。
読者の心を動かすのもストーリー
もちろん、体験談が強いのはAIだけの理由ではありません。
人間の読者にとっても、体験談は共感を呼び、心を動かす力を持っています。
観光客なら「自分もその景色を見たい」とワクワクし、
美容院のお客さまなら「同じ年代の人がそう感じたなら私も似合うかも」と安心する。
建築のお客さまなら「この家で暮らす未来」をイメージできる。
体験談は、情報を「感情に変えるスイッチ」なんです。
ビジネス発信での活かし方
体験談を盛り込むのは難しく思えるかもしれませんが、コツはシンプルです。
- 自分自身の体験を書く
(例:「僕が初めて釧路の炉端に行ったとき…」) - お客さまの声をストーリーとして紹介する
(例:「先日、阿寒湖の宿に来たお客様が『朝食のいくら丼に感動した』と教えてくれました」) - 日常の小さな出来事を入れる
(例:「SNSで常連さんに『今日のおすすめは?』と聞かれたんです」)
ちょっとした気づきやエピソードで十分。むしろ短く具体的な方が伝わりやすいです。
文章に命を吹き込む
体験談やストーリーを入れると、文章に命が宿ります。
同じ情報でも「生の声」が加わることで、読者は「自分ごと」として受け止めやすくなる。
AIはその具体性を拾い、検索や推薦のリストに載せやすくなる。
人とAIの両方に効く、それが「体験談の力」です。
まとめ
体験談・ストーリーを盛り込むことは、AIO対応=LLMO・GEOに強い発信をつくるための大切な要素です。
- AIにとっては「信頼できる具体的な情報」として認識される
- 読者にとっては「感情を動かす物語」として届く
- ビジネス発信でも小さな出来事を入れるだけで効果がある
一般論より、ほんの少しの体験談。
それが文章を“生きた情報”に変えてくれます。
藤村 正宏
最新記事 by 藤村 正宏 (全て見る)
- AIは未来を決めない。未来を強化するだけ - 2026年1月29日
- 好奇心を失っていない人には 楽しい毎日 - 2026年1月28日
- 「日本は借金大国」は本当なのか? それって「都市伝説」レベルの話だよ - 2026年1月25日