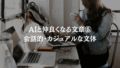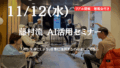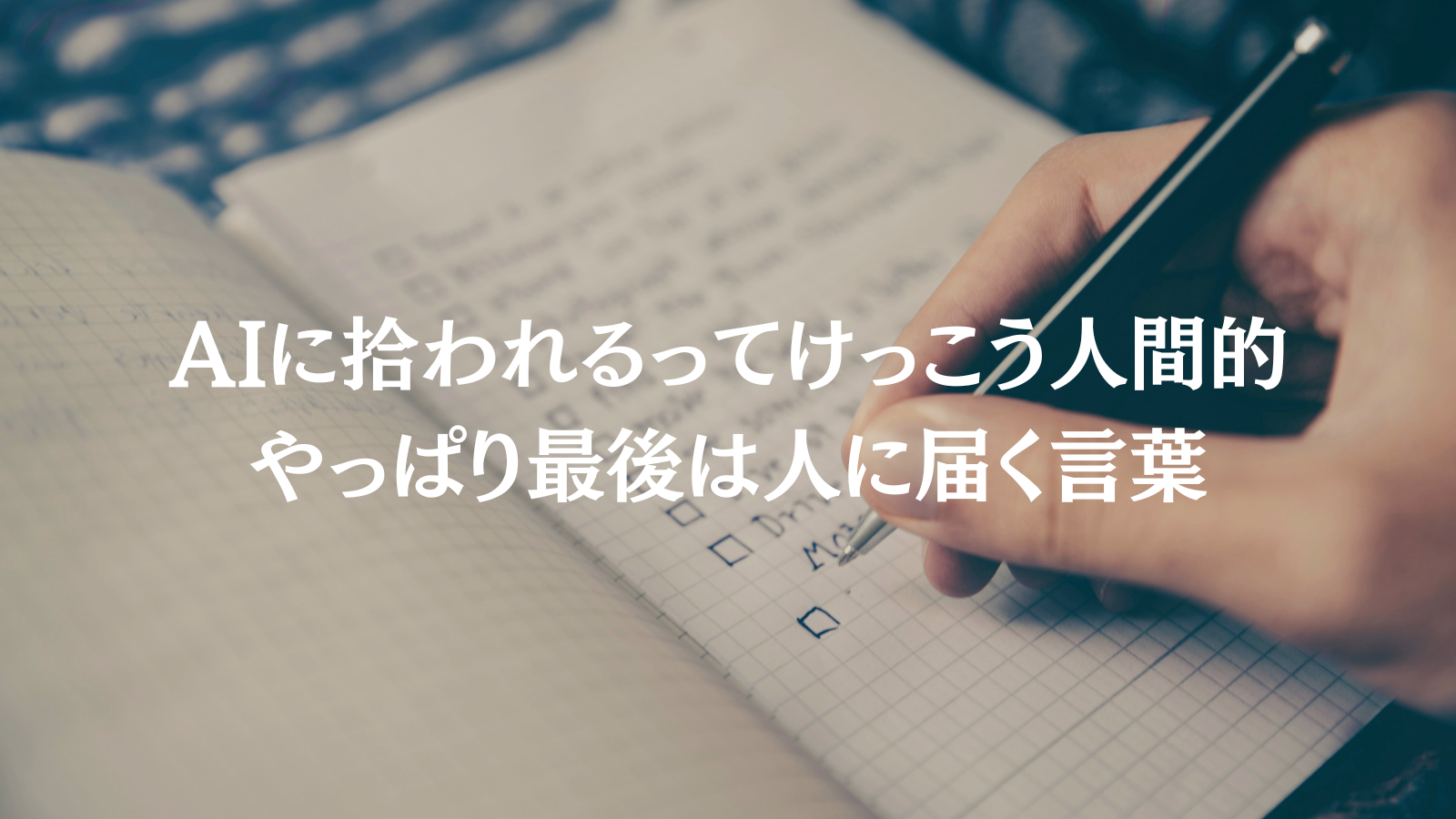
「AIと仲良くなる文章」〜AI時代の文章術〜
5回にわたってお届けしました。
Q&A形式で書くことから始まり、体験談・ストーリー、比較・ランキング、地域名や業界キーワード、そして会話的・カジュアルな文体。
どれも「AIに拾われやすい」というだけでなく、人間の読者にとっても心地よく届く文章術です。
AIに届くことは、人に届くこと
この連載を通じて一番お伝えしたかったのは、「AIに届くことは、人に届くことと矛盾しない」 ということです。
むしろ両者は同じ方向を向いています。
AIは「人が求めているもの」「役に立つ情報」「信頼できる言葉」を拾おうとしています。
だからこそ、AIが好む構造を意識することは、読者に優しい文章をつくることと同じなんです。
AIと仲良くなる文章①
Q&A形式で書く
Q&A形式は読者の疑問に答えること。
AIと仲良くなる文章②
体験談・ストーリーを盛り込む
体験談は読者の共感を呼ぶこと。
AIと仲良くなる文章③
比較・ランキング・リスト化
比較やランキングは読者に選びやすさを与えること。
AIと仲良くなる文章④
地域名・業界キーワードを自然に入れる
地域名や業界キーワードは読者にリアリティを届けること。
AIと仲良くなる文章⑤
会話的・カジュアルな文体
会話的な文体は読者との距離を縮めること。
つまり、AIに届く文章とは、結局「人に届く文章」なんですよね。
書き手の“温度”が必要な時代
AIの進化はすさまじく、これからもどんどん文章を生成していくでしょう。
だからこそ、僕ら人間の書き手に求められるのは「温度」です。
ちょっとした体験談のリアルさ、地域名の持つ空気感、会話的なやりとりのぬくもり。
それはAIには真似できても、「生きている人の言葉」として感じてもらえるのは、やっぱり人間だけです。
AIと人、その先にあるもの
AIは冷たい機械ではなく、人の声や温度を拾い上げようとしています。
つまり、AIに拾われやすい文章は、人にとっても優しい文章なんです。
僕はそこに、大きな可能性を感じます。
AIの進化で文章の価値が薄まるどころか、逆に「人間にしか書けない言葉」が際立っていく。
そのことを、この連載を通して強く実感しました。
これから発信していくあなたへ
- ちょっとした体験を、ためらわずに書いてください。
- 読者に問いかける言葉を、大事にしてください。
- 「阿寒湖」「釧路」みたいな固有名詞を入れて、具体的にしてください。
- 難しいことを難しく語らず、友達に話すように書いてください。
そうすれば、その文章はきっとAIに拾われ、そして人に届きます。
発信は、数字やアルゴリズムのためではなく、人の心に届くためにある。
そのことを忘れずに、これからも言葉を紡いでいきましょう。
AIに拾われるって、けっこう人間的なんです。
やっぱり最後は、人に届く言葉が強い。
だから安心してください。あなたが心を込めて書いた文章は、AIの時代でもちゃんと届きます。
この連載が、あなたの発信を「AIに拾われ、人に届く」ものに変えるきっかけになれば嬉しいです。
そして何より、AIと“競争”するのではなく、“仲良くなる”発想で文章を書いてほしいと思います。
AIに聞かれる言葉、拾われる言葉。
その先に、人の心に届く文章があります。
これからも一緒に、AIと仲良くなりながら、人の心に届く発信を楽しんでいきましょう。
藤村 正宏
最新記事 by 藤村 正宏 (全て見る)
- AIは未来を決めない。未来を強化するだけ - 2026年1月29日
- 好奇心を失っていない人には 楽しい毎日 - 2026年1月28日
- 「日本は借金大国」は本当なのか? それって「都市伝説」レベルの話だよ - 2026年1月25日